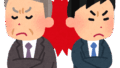週刊現代2025年11月10日号に、元自民党税調トップの宮沢洋一氏が、
「税調会長としてやり残したことと言えば、政府による国民の所得と金融資産の把握です。
米国には社会保障番号があり、政府は個人の所得を知り得ますし、金融資産についても少なくとも国内にあるものは把握している。おそらく先進国はほぼすべてそういう状況なんです。
ところが、日本には国民の資産を把握する術が本当に何もありません。たとえば、コロナ禍の時に問題となりましたが、給付金を支給しようにも誰の所得が少なくて、誰が金持ちなのかさっぱりわからないわけです。政府が把握できているのは、基本的に年金収入くらいです。
しかし、年金収入が少なくても、莫大な金融資産を持っている人もいます。そういう人にも給付金を支給してしまうのは、不公平だと思いませんか。
一般の人たちは、口座の中身を政府に知られたからといって困る話は何もないはずなんです。むしろ困るのはお金持ちたちですよ。過度の節税はできなくなりますし、資産家を狙い撃ちした課税ができなくもないですから。
しかし、政府が国民の資産を把握すると言うと、個人情報保護の観点から常に反対が起こって潰れてきた歴史があります。
ただ、維新は社会保険料の負担軽減のために金融所得の把握実現に熱心だったはずなので、連立政権でこれを進めていってほしいですね。」
とコメントしてました。このインタビュー、ぶっちゃけコメントが多くて面白かったです(苦笑)
以前(記事はこちら)も書きましたが、元税調トップがここまで「国民の金融資産把握の難しさ」を強調してるわけで、今後も「金融資産への課税や社会保険料反映」は実現しなさそうです。
ということは、近い将来、最後のコメントにある「金融所得」にメスが入りそうです。
おそらく、近々「金融所得」は「分離課税」か「総合課税」の選択制となり、「分離課税は20%から税率アップ、総合課税は社会保険料へ反映」というシナリオが有力そうですかね・・・
私も株式(記事はこちら)は「NISA」「iDeCo」「特定口座」と税制が違うもので保有してますが、税や社会保険料の制度動向をよく観察して、今後の取り崩し方法を思案しようと思います。