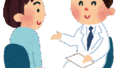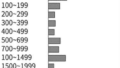日経新聞夕刊2025年9月19日に「スーパーマーケットは東京を目指す」という記事で、
「有力スーパーが一斉に東京を目指している。日本全国ほとんどの都道府県で人口が減少するなか、東京一極集中が強まり各社の背中を押す。
トライアルは買収した西友と連携し、今秋にも都内に小型店の出店を始める。イオンはネットスーパーと小型店の両軸で攻勢を強める。価格競争が激化し、コンビニにとって大きな脅威となる。
「現状、流通業では少子高齢化と都心への人口集中を、どこの小売業も課題に挙げている」とトライアルの野田執行役員は語る。将来を見据えれば、東京攻略は不可避なテーマなのだ。
人口が集まる場所にイノベーションも集中する。新勢力が安さなど新たな魅力を都内の顧客にアピールすれば、迎え撃つコンビニや既存のスーパーは現状維持では生き残れない。
必死で対抗策を練るだろうが、淘汰される店舗も出てくるはずだ。コンビニが価格勝負を避けるなら、商品やサービスで新たな魅力を生み出さなければならない。
激しい競争は都民にはメリットがありそうだが、懸念されるのは地方との格差だ。人口減少で小売店舗の撤退が進むようだと、生活が不便になって地方の衰退をさらに進める恐れもある。」
とありました。埼玉県が地盤のヤオコーも今年6月に慎重だった都内出店に踏み切ったとのこと。
「東京の方がむしろ生活費が割安?」(記事はこちら)でも書きましたが、食料品や日用品といった領域でも、イオンやアマゾンを活用すれば、都心でも割安に購入できるようになりました。
この記事を読んでいて思ったのは、「サラリーマン時代は飲料や嗜好品購入でコンビニをよく利用していたのに、FIRE後はめっきり使わなくなったな・・・」ということでした。
それは、オフィス勤務の時は一刻を惜しんでビルの1Fにあるコンビニを利用していたのが、FIRE後には家の近所の割安なイオンを利用するようになった、という変化が大きいと思います。
ちょうど同日の日経MJでファミマの細見社長が「加工食品や飲料は(値引きなしの)プロパー価格で売ってます。今やプロパー価格はコンビニと自販機くらい」とコメントしてました。
一方、最近の昼休みの時間帯の近所のイオンはサラリーマンが多くとても混雑してます。食料インフレで、サラリーマンもコンビニで買うのを控えて、価格重視になっているように感じます。
果たして、コンビニは「価格勝負を避けるなら、商品やサービスで新たな魅力を生み出さなければならない」を実現できるのでしょうかね・・・かなり難しい課題になりそうです。
都民としては、価格競争は歓迎ですし、付加価値向上も歓迎ですので、良い流れですかね・・・