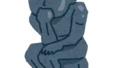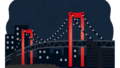日経新聞朝刊2025年9月6日に「消費税」の特集記事があり、吉川洋・東大名誉教授が「消費税には手をつけない」と明言していた当時の小泉首相にその理由を尋ねたところ、
「最初に消費税を上げると言ったら、誰が歳出効率化を真面目にやりますか。自分は効率化に努めて消費税は次に託す」
と述べた、とありました。ちなみに「小泉政権」は2001年〜2006年まで続きました。
私は、日本の歳出効率化はある程度、小泉政権時代に進んだのではないか、と考えてます。実際、その後の政権交代時に当時の民主党が色々騒ぎましたが、ほぼ成果が無かったわけですから。
そうなると、結局は「社会保障費」の負担をどうするか、に焦点は絞られてきます。
「社会保障」は一般的に「個人の責任や自助努力では対応し難い不測の事態に対して、社会連帯の考えの下につくられた仕組みを通じて、生活を保障し、安定した生活へと導いていくものである」と定義されてます。この考え方と仕組みは今後の日本にも残すべきだと私は思います。
具体的には「年金」「医療」「介護」「福祉」等になります。足元で合計140兆円(国と地方の税金負担がそのうち約4割)と圧倒的規模で、今後も高齢化により増えていくことが不可避です。
これをどう「税金」「保険料」「自己負担」で分け合うのか、「分断」ではなく「社会連帯」を維持するためには「全世代で応能負担するしかない」という結論は何度も繰り返されてます。
一部には「大企業」や「富裕層」に負担させれば良いという意見もありますが、それでは大した財源にならずに、社会の活力が失われてしまうでしょう。
記事では「所得が基準になる保険料は現役世代に負担が集中し、年金生活の高齢者の負担は軽くなる。これに対して消費活動には所得だけでなく資産の保有状況も反映される。そこに課税すれば、資産がある高齢者に応分の負担を求める構図になる」とも書かれてました。
税金や保険料の負担逃れに長けた目端の利く人も「消費税」だけは逃れにくいという現実もあります。やはり今こそ「消費増税」に国民理解を得られる日本の政治家の登場が待たれます。
現実の選挙結果は全く逆方向ですが、仮に「消費増税」に成功すれば、日本の財政規律に対する市場の信頼が回復し、通貨(日本円)の価値も保持される、という最重要案件も期待できます。
平和な東京でFIRE生活を送りたい私は、消費税率「20%」程度までは前向きに負担しようと思っているのですが、そういう意見が「民意」になる日は果たして来るのでしょうかね・・・