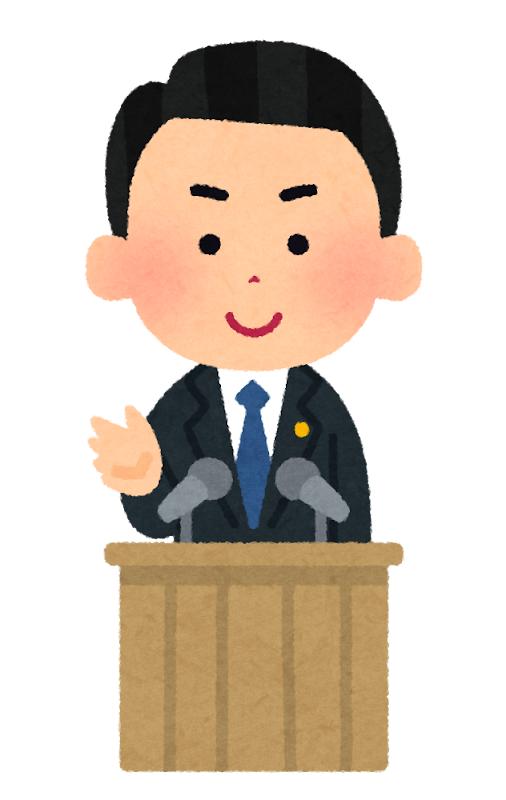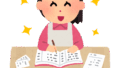日経新聞朝刊2025年7月24日に編集委員の柳瀬和夫氏が「消費税なき社保改革の難路」として、
「参院選では消費税の不人気ぶりが浮き彫りになった。野党が訴えた減税が現実味を帯びる一方、税率10%超への増税ハードルは著しく上がったとみるべきだろう。
社会保険料は原則として所得に比例するので負担を求める対象が現役世代に集中してしまう。一方、消費税は所得が少ない高齢者にも支払い能力に応じた負担を求めることができる。
世帯の消費活動には所得だけでなく、預貯金、株式などの金融資産や不動産の保有状況が反映されるからだ。株価が上昇した時に生じる「消費の資産効果」などがその実例だ。
つまり、社会保障の財源に占める消費税の比率を高めていけば、精緻な応能負担の仕組みではないにせよ、現役世代に偏る負担を引退世代にも分かち合うことが可能となる。
だが、消費税の追加導入という手段が取れない現状で負担の改革を進めるには、社会保険料の算定に金融資産の保有状況を勘案する仕組みをつくるしかない。
ただ、この設計は一筋縄ではいかない。「住宅ローンなどの金融負債の扱い」「金融資産把握の基準日の抜け道塞ぎ」「NISAなど税制優遇口座の扱い」「そもそも行政が網羅的に国民の金融資産を把握できるのか」といった課題がある。これらの課題は20年以上前から議論されている。
消費増税ができないのならば、金融資産の社会保険料負担反映の仕組みづくりを先送りすることは許されないが、極めて難路である。」
と書いてました。確かに「消費増税」は当面極めて難しいというのが現実なんでしょうね・・・
とはいえ「金融資産」を「社会保険料」に反映させる仕組みを作ることも極めて難しそうです。
柳瀬氏も指摘してますが、消費税は精緻ではなくても概ね「応能負担」を実現でき、しかも「税逃れ」が最も難しいと言われる課税スキームです。払いたくない人は消費しなければ良いですし。
このあたり分かりやすく説明でき、国民に納得感をもたらすことのできる政治家の登場に期待したいものですね。平和な日本でFIRE生活を満喫したい私としては、基本的に消費増税に賛成です。
それにしても、もし「個人の金融資産」を政府が本格的かつ網羅的に把握しようとしたら、すさまじい「税逃れ」や「裏ワザ」が横行し、収集がつかなくなるでしょうね・・・