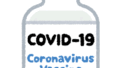日経新聞朝刊2025年11月20日にフィナンシャル・タイムズ記者の記事として、
「米国はかつて、自らを中流層の国と見なしていた。同じ夢、同じ娯楽、大衆向けブランドを受け入れるという共通点で国民が一つになっていた。
ころが今や、最大限の利益を引き出したい企業が、消費者を「持つ者」と「持たざる者」、そして「ヨットまで持てる者」といったように、所得階層によってえり分けることに熱を上げている。
短期的に利益を得る観点からすると、この戦略は全く理にかなっている。米経済は所得格差が極めて大きく、最上層が経済的繁栄を享受する一方、残りの人々は家計のやりくりに苦しんでいる。
米国の所得上位10%の支出は目下、消費全体の約半分を占めている。1990年代には3分の1ほどだった。こうした人々の多くは株高の恩恵を受け、懐が潤っている。
最も高級志向な消費者を対象にしている企業であっても、富裕層の気を引くだけでは生き残れない。あるCEOによると、高級品が高く売れるのは、社会の幅広い層で憧れの的である必要がある。
しかし、米社会で上昇志向を持てなくなっている人は増えている。追加課金のマーケティングに頼っている企業は、今の顧客が世代交代を迎えた時に後悔するかもしれない。」
とありました。
日本に住む私も、最近「ラグジュアリーゾーン」の価格帯が、だんだん世の中から分断しているのを感じてます。最上層に特化したホテル・旅館・レストランが増えてきているのです。
もはやその価格帯は「大衆が手を伸ばせば届く」ところからは遠くなり、日本人のスーパーリッチやたまに日本に来る富裕層外国人だけを相手にするようになっているように感じてます。
しかし、私の考えでは、この状況のリスクは「世代交代の時」だけでなく、時間の経過と共に「品質(味)」や「サービス」の低下リスクも大きいのではないだろうか、と思ってます。
というのも、ハレの日に吟味を重ねて、ホテル・旅館・レストランを利用していた富裕層寄りの「大衆」は味やサービスに厳しく、それによってサービス側は常に切磋琢磨してきたわけです。
その「市場メカニズム」が失われると、当然サービス側は徐々に実力を落とす可能性が高いでしょう。そういう観点で「会員制のサービス」は大抵長続きしないようにもいつも感じてます。
そして、株式市場の暴落等で不況が来ると、そういうサービス側は一気に淘汰されるのでしょう。私としては今後も「大衆の手の届く」価格帯で勝負している所に通い続けようと思います。