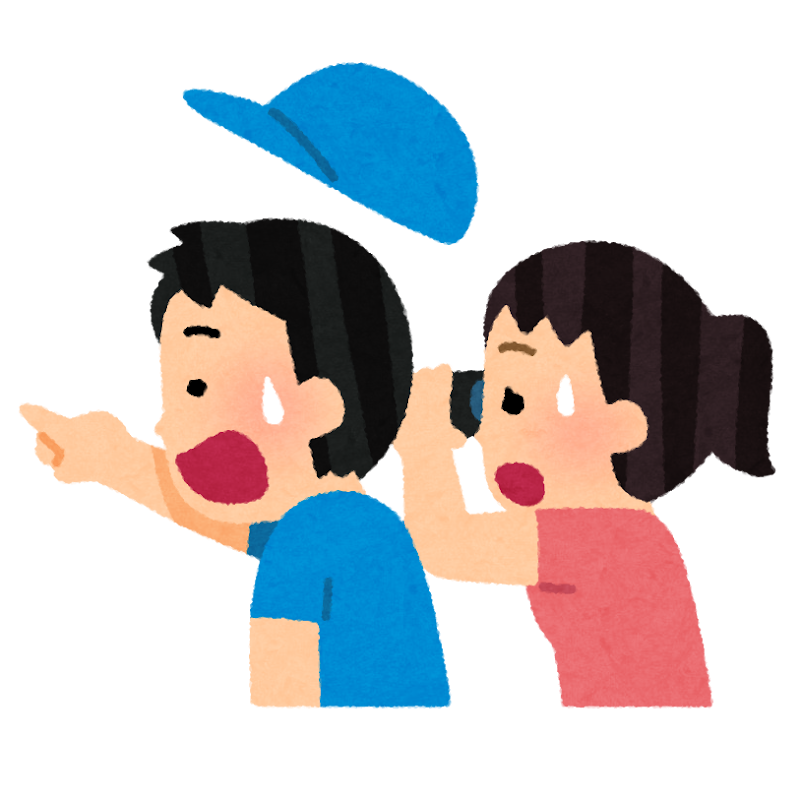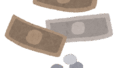週刊新潮2025年11月20日に脳研究者の池谷裕二氏が、
「ある実験で賞金探しをさせたところ、多くの人が「予測不能なランダムに行き先が決まるエリア」で多くの時間を過ごす傾向があることが分かりました。
興味深いのは、既に賞金を十分に獲得し寄り道する必要のないグループも、その「ご褒美のない遊び場」にかなりの時間を費やし、過剰なまでに探索を続けたことです。
彼らを動かしたのは、賞金への期待ではなく、まだ見ぬ世界への抑えきれない「好奇心」ともいえるものです。この好奇心の正体は何でしょうか、実験をした研究者が検証しました。
1つ目は、自分の知識の不確かさを減らしたい「情報獲得モデル」です。頭の中の地図を完成させたいという欲求です。2つ目は、予測が裏切られることに興奮する「驚き」モデルです。そして、3つ目が、まだ訪れた回数の少ない、目新しい場所へ行きたがる「新奇性」モデルです。
結果、ヒトの行動に最も合致したのは「新奇性」モデルでした。ヒトは曖昧なことをハッキリさせたいわけでもなく、ただひたすらに、まだ体験したことのない「新しいもの」を求め、それに価値を感じるようです。たとえそれが、最終的な目標達成の妨げになったとしてもです。」
と書いてました。人間はただひたすら「新しいもの」を求める、ですか・・・興味深いですね。
確かに私も東京都心の街歩きをしている時、数は少なくなりましたが「未知」の街を歩く時は脳が少し興奮していることに気付きます。その「新奇性」が、脳を刺激するのでしょうかね・・・
ただ「なじみ」で「好きな」の街を歩いている時は、深くリラックスして心地良いです。海外も色々行った結果、毎年ひたすら「ハワイ」(というかハレクラニ?)に行くようになりました。
街歩きも東京メトロネットワークカレンダー(記事はこちら)の範囲は、一通り歩いてみたいですが、その後はいくつかに絞られた「なじみの好きな街」をひたすらリピートしてる気がします。
そう考えると、私はどうも「頭の中の地図を完成させたい」タイプなのかもしれません・・・