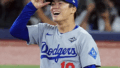日経新聞朝刊2025年11月8日に、
「物価高が続く中、多くの人が節約を考える食費。総務省「家計調査」で2025年1~8月の支出を物価変動の影響を除く実質で比べると食費は前年より1.4%減っている。
「高校生の息子のため割安な鶏肉頼みが続く」。東京都在住の40代女性は話す。鶏肉を使って節約に努める。「ハンバーグも牛と豚の合いびき肉に鶏肉、豆腐も入れてボリュームを出す」という。
専門家は「食費節約は限界が近い」と話す。一般に夫婦と子の3~4人世帯なら「食費は手取り月収の12~15%程度が目安。既にそこに近い家計が多い。10%を切る『やり過ぎ』懸念の例も散見される」と話す。
さらに安い食材を選んでも費用を減らし続けられるとは限らない。例えば、冒頭の女性が話す鶏肉の安さも揺らぐ。総務省「消費者物価指数」でみると鶏肉は25年9月に前年同月比10.6%プラスと、上昇率では肉類で最高となった。」
とありました。
日本のエンゲル係数の平均は30%弱なので、この場合「外食」等を除く「食料品代」のことを言っているのですかね・・・それにしても一部の家計はかなり追い詰められているようです。
足元は実質賃金が増えていないので、資産インフレで「家計の緊張」を緩和したい局面ですが、資産形成期初期の人はそれも叶わず、更なる「支出減」と「給与所得増」を目指すしかありません。
そう考えると、私のように資産形成期がずっと「デフレ期」だった世代は、不動産や株式を安く買える期間が長く続いたという意味では、決して悪い環境では無かったのかもしれませんね。
ただ、新卒での就職の結果(安定した給与所得の有無)が、その後の明暗を分けましたが・・・