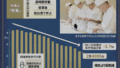日経新聞朝刊2025年10月12日に、
「憎悪と経済の関係を深掘りした英ブラッドフォード大のキャメロン教授は、憎悪が単なる心理的、社会的現象でなく「効用の最大化」という経済学の基本原則から理解できると説く。
ポイントは「効用」が物理面・金銭面にとどまらない点だ。たとえば移民の排除で経済が傷めば狭くは「非合理的」でも、優越感や不満の発散、政治的一体感など別の領域で満足感を得られれば十分に理にかなう。この心理的満足感には中毒性があり憎悪を補強・継続させるとも指摘した。
一方、憎悪を生産者と消費者の取引に見立てたのが米ハーバード大のグレイサー教授だ。生産者たる政治家は支持や献金、得票といった利益を狙って憎悪を振りまき、これを有権者が消費する。憎悪の需要が増すのは生活苦などで不満を宿す有権者が自らの感情・偏見と共鳴する言説に繰り返し触れたとき。真偽を検証する動機は薄いため、うそと憎悪が自己増殖しやすいとした。
ともに憎悪は非合理的でなく、理にかなうゆえに継続・拡大するとの指摘で、今後の米世論と政策を占う上で示唆に富む。経済に悪影響が広がっても、あるいは広がればなお、よそ者を排する動きが勢いづく懸念は拭えない。」
とありました。
「憎悪の心理的満足感には中毒性があり憎悪を補強・継続させる」というのは、残念ながら人間の本質を突いているかもしれません・・・
日本でも「ヒトの不幸は蜜の味」という言葉もあり、文春砲などの社会的バッシングを通じで、「物理的・金銭的効用」ではなく「心理的効用」を求める人が結構多いような気がします。
そんな人が多数派になりつつあるのが、最近の世界の情勢なのかもしれませんね・・・