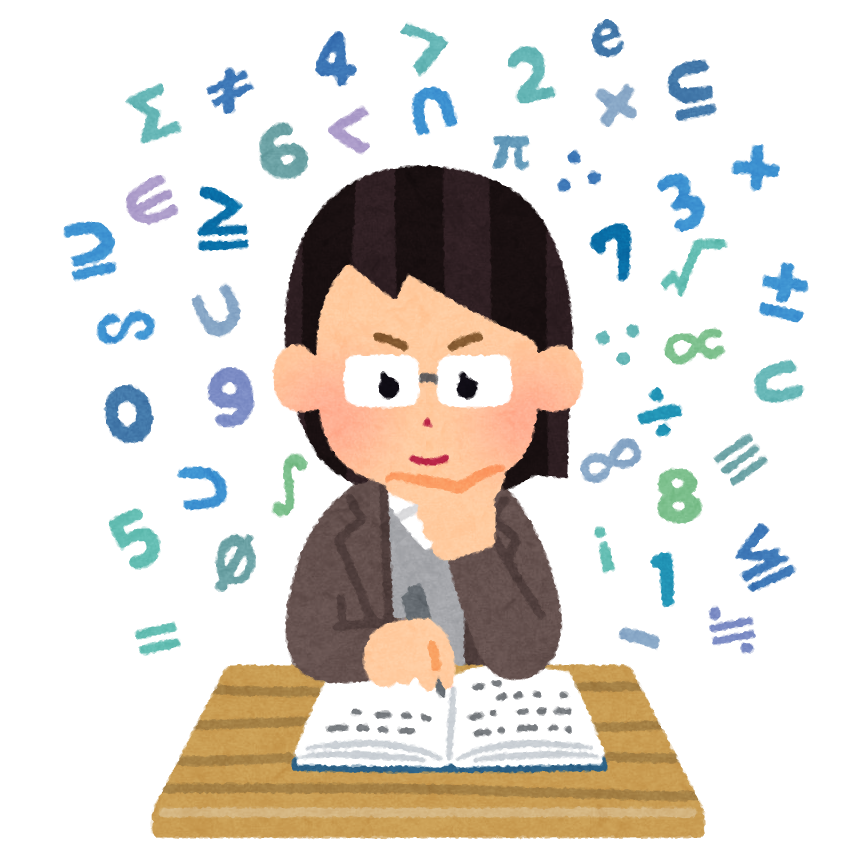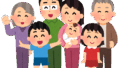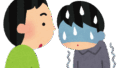日経新聞朝刊2025年10月4日に「基礎科学の火を消さない」という特集があり、
「日本は経済への貢献や効率性を求めすぎた結果、科学力の低下は著しく、研究現場には閉塞感が漂う。いずれ技術革新の芽は少なくなるだろう」
とありました。同時にノーベル生理学・医学賞受賞者の大隅良典氏がインタビューで、
「日本は好奇心に基づく研究ができなくなってきている。日本は流行のテーマだから研究しなければという意識が強いが、世界との競争の中で勝ち抜くのは難しい。
各研究者が「本当に興味あるテーマ」「好奇心から生まれる研究」「より自由な発想のまだ小さな研究」にある割合の資金を充てることが必要だ。
私がノーベル賞を受賞することになった「オートファジー」も老化予防などにつながる可能性があり、応用研究が盛んになってきた。しかし、私は知りたい、面白いと思って研究を続け、役に立つことを意識したわけではない。」
とコメントしてました。
私も学生時代・社会人時代を通して、優れた科学者になれそうな資質を持つ人と会話をすることが何度かありましたが、そういう人はほぼ全員「独特の強い好奇心」の持ち主でした。
また、あまり社会性を感じず、FIRE民とは真逆で経済的な関心も低めの人も多かったように思います。おそらく圧倒的上位の人生の優先順位が「自分の知的好奇心を満たすこと」なのでしょう。
そういう人材がのびのび活躍できる場として、国公立大学の研究機関には、ある程度おおらかに基礎研究予算を税金から投入しても良いのではないでしょうかね・・・
やり方は、未来の科学技術の評価を現時点ですることは不可能と割り切って、ずば抜けた理数系の能力を持つ人材に自由研究の終身雇用ポストを与える、というシンプルな施策で良いと思います。
「ずば抜けた理数系の能力」をどう測るかは論点ですが、高校くらいまでにペーパーテストでもある程度は見分けられるのではないでしょうか。その後、大学・大学院で最終選抜する形で。
仮に年間1000万円を5万人の自由研究をする基礎研究者の人件費に充てたとしても年間5000億円の予算に収まります。それくらいの余裕やゆとりは今後の日本にもあってほしいものですが・・・