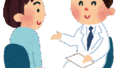日経新聞朝刊2025年9月17日に、
「令和国民会議(令和臨調)は恒久的な減税に対し、(1)減税に見合うだけの歳出を減らす(2)別の税目で増税して恒久的な代替財源を確保する――という財政に中立的な対応を求めている。
赤字国債の増発で補うのでは人口が細る後世代へのツケの先送りとなり、将来の増税やインフレで返すことになる。
気がかりなのは消費税減税の支持者に「自国通貨建て国債ならいくらでも発行できる」「発行した国債は借り換え続ければいい」といった言説が広がっていることだ。
本当だろうか。こうした問いに対する解は歴史に学ぶほかない。
自国通貨の円建て債ならばデフォルトは起きないのか。「銃後のご奉公」として戦時国債の消化や貯蓄を強いられた国民に報いることはできたのだろうか。
結論から言えば、日本は額面、つまり名目上は債務を履行した。だが、戦後の激しいインフレで実質的な価値は失われ、戦時国債は紙くず同然になっていた。
2035年を基準とした日本の消費者物価指数は45年までに約6倍、さらに2049年までの4年間で約30倍に上昇している。2035年比で国債の実質価値がインフレで180分の1に縮んだおかげで、あくまで名目上、政府は借金を返せたにすぎない。」
とありました。結局、戦時中の赤字国債は「ハイパーインフレ」で解決したということですね。
戦時中の1944年でも国債残高の名目国民総生産(GNP)比は「197.4%」だったそうですが、現在の国債残高はGDP比で「2倍」を超えています。財政的には戦時中と似たような状況です。
ただ、戦時中は「軍事費」が国家予算の8割を占めてましたが、現在は国の一般歳出に占める比率で「社会保障費」が56%と突出してます。高齢化により「社会保障費」は今後も増加します。
記事では、現在の日本政治は「次の選挙のことしか考えない政治屋(ポリティシャン)」か「次の世代のことを考える政治家(ステーツマン)」かが試される局面とありましたが、まさしく・・・