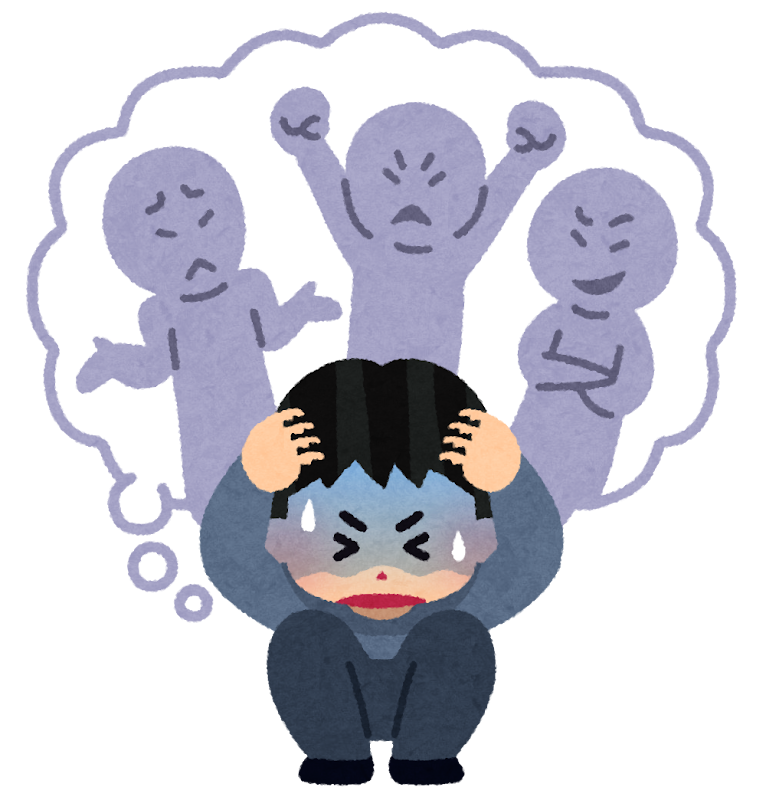「自分は「底辺の人間」です」(京都新聞取材班・講談社)という本を読みました。
京アニ放火事件のルポタージュで、以前、朝日新聞取材の同様の本(記事はこちら)を読んでいたのですが、事件の地元の京都新聞の取材ということで「新たな視点」を期待して購入しました。
青葉被告は「不遇な氷河期世代が陥りがちな「一発逆転の呪い」に絡め取られ、こつこつ努力しても報われないから、突飛な方法で成功を夢見て「小説」を書き、京アニに応募するも不採用、それを「パクられた」と妄想し、憎しみをたぎらせて凶行に及んだ」というのが本書の分析でした。
裁判では「自分は底辺の人間で、力でねじ伏せて黙らせるという「底辺の論理」で生きてきた。事件当時はこうするしかないと思ったが、こんなにたくさんの人が亡くなるとは思っておらず、やりすぎたと思っている」という、亡くなった36人にとって極めて理不尽な発言もしています。
今回の本でも、私はそんな青葉被告でも犯行直前に逡巡した十数分間に興味を覚えました。
妄想がひどくなり統合失調症と診断され、精神科の治療や訪問看護などの「社会保障・福祉」は実施されていたが、自身で拒絶(現場の看護師などは暴言を受けながらも粘り強く接触)します。
そして、犯行数日前にATMで全財産5万7000円を引き出し京都に行き、ガソリンを購入後に所持金も尽きた後、本当に犯罪を実行するべきか、「十数分間」逡巡します。
その時「自分にも良心が残っていて悩んだ」と後述しますが、それでも京アニへの筋違いな憎悪が勝り、結局犯行は実行されてしまいます。最後の分かれ道も最悪な選択になってしまうわけです。
青葉被告は以前別の事件で逮捕された時に「お金がない。友だちもいない。人生どうでもいい。生きていても意味ない」と供述しているそうです。
そこまで追い詰められても「自責思考」の人は、犯罪ではなく最悪の結果として「自殺」を選んでしまうのでしょう。
しかし、青葉被告のような「他責思考」の更にごく一部の人が、今回のような「無差別殺人」を起こしてしまうということなのでしょうか・・・
日本の社会保障が目指している「社会の連帯維持」の為、青葉被告に関わった福祉の現場の方は、それぞれ努力されていたことが、この本でも確認されています。
一方、事件で重度の全身やけどになった青葉被告を救命し、長い時間本人と直接関わった医師の上田敬博氏は「彼は稚拙なんですよ」とコメントしたそうです。
そんな個人が起こした事件で、あまりに多くの人命が奪われ、遺族や関係者がきわめて深い苦しみを背負う理不尽さは、司法の「極刑」という判断だけでは解決できないでしょう。
しかし、私にもそれ以外に解決法も思い浮かばず、今回も後味が悪い読書となりました・・・