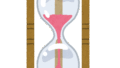日経新聞朝刊2025年8月15日の「経済教室」で牧野邦昭・慶応義塾大学教授が、
「参院選では与党が給付金、野党の多くが消費税減税を主張し、与党が過半数割れと大敗した。この結果の一つの解釈として、日本の有権者は給付金による富の再配分を目指す「大きな政府」ではなく、減税して民間の活力を生かす「小さな政府」を志向しているということもできる。
小さな政府を好ましいと考えるのは、政府による富の再配分を嫌い、自助努力が望ましいとする価値観の表れと考えられる。この価値観の形成には、江戸時代後期の二宮尊徳の思想による影響が大きかった。当時、尊徳らは荒廃した農村を再建するため農民の自助努力を説いた。この考えが社会に広まるにつれ、「貧しいのは怠けているから」という価値観が形成された。
明治維新により封建制度が崩壊すると、人々は自分の力で生きることを余儀なくされる。そこでよりどころとされたのが江戸時代から続く二宮尊徳的価値観と、西洋資本主義の価値観だった。
それは戦後も粘着的に継続し、1990年代以降は個人や企業の自助努力による局所最適化が逆に様々な問題も引き起こしている。とはいえ歴史を振り返れば、価値観が大きく変わるとは考えにくい。そうであれば、むしろ自助努力を良い方向に導く必要がある。
自助努力の成果を可視化する方法としては賃上げがわかりやすい。現在の国民の不満の根底には、賃上げが物価高に追いついていないことがある。賃上げが促進される政策を実行し、自助努力により生活が良くなる「実感」を多くの人が共有することが重要だ。それがひいては経済を発展させ、社会を安定させると考えられる。」
と書いてました。「勤勉さ」や「自助努力」という価値観は、江戸時代後期の二宮尊徳の影響が大きいんですね。確かに、昔は色々な小学校に「二宮尊徳像」がありましたね・・・
この「二宮尊徳的価値観」と「FIRE」は相性が悪いようで、氷河期より前の世代と話すと、多くの場合「勤労の義務があるのだから無職(FIRE)なんてありえないだろう」的な反応があります。
ところが、氷河期以降の世代と話すと「FIRE」に前向きな反応が多い印象です。「FIRE」という新しいワードのカジュアルさや、リーマンショック以降続く株高トレンドも背景にありそうです。
この記事の牧野邦昭・慶応義塾大学教授は「1977年生まれ」の氷河期世代。「二宮尊徳的価値観が大きく変わるとは考えにくい」という考えのようですが、どうでしょうかね?