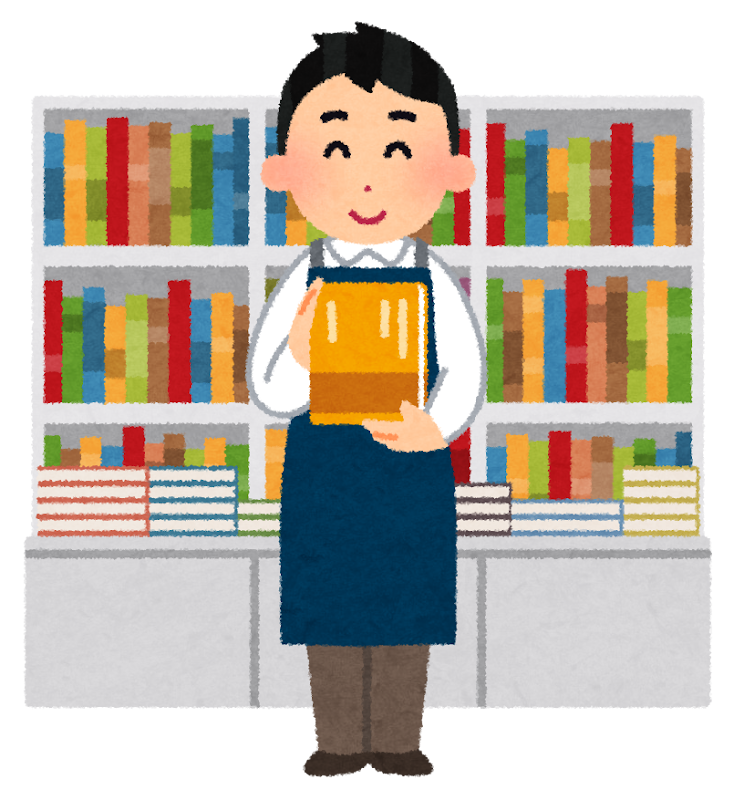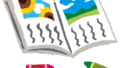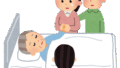日経新聞朝刊2025年5月24日に「町の本屋はいかにしてつぶれきたか」の著者・飯田一史氏が、
「新刊書店は価格決定権がほぼなく、22%前後とされる小売業ワーストクラスの粗利益率が原因で商売を難しくしている。
日本は他の国に比べると本が安くて素晴らしいといわれるが、それはあくまで消費者視点の話。本屋からすれば全然ありがたくない。
確かに最近は本の値段が上がって嫌だなと思う気持ちもよくわかるが、本が与える価値に応じて適正な値段がついてしかるべきだと感じてます。」
とコメントしてました。私も「町の本屋はいかにしてつぶれきたか」を読み進めている最中なのですが、著者の市場分析の解像度の高さと知らなかったことが多いことに驚いてます。
元々の粗利の低さに加え、雑誌が売れなくなってきていることが、町の本屋が苦戦する大きな理由だそうですが、私自身は好奇心をくすぐられた本は、ほぼ値段を見ずにどんどん買ってます。
経験を重ねて明らかなハズレの本を買うことは少なくなり、読み終わった後、本の値段が高いと思うこともほぼ無いので、確かにその価値に比べて値段が安い本が多いのかもしれません。
書店自身にも流通構造の変革や不要なコストカットは今後も進めてほしいですが、書店の取り分が増えて今後も健全な書店経営が続くなら、本の多少の値上げは私は構いません。
ただ、せっかくの本屋のスペースが粗利の高い雑貨やシェアラウンジで埋まるのはあまり賛成ではないですね・・・あくまで本屋としてスペースをフル活用する方向を歓迎したいと思います。